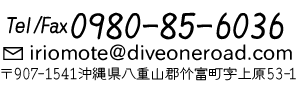リピーターさんが「夜も楽しみたい」と、ナイトツアーに行きました。
アオバズク発見。

見えないけど、道路に下りている子もいましたよ。

多くの個体と会うことが出来ました。

昼間にはあまり会わない生き物がたくさん活動しています。

ヤシガニはたくさんいますよ~。

ちょっと気持ち悪いという方もいるかな?!
オオシママドボタルの幼虫とアシヒダナメクジのコラボ。

ナナフシは昼間でも見られますが、葉っぱを食べている姿はなかなか見られません。
写真では伝わりにくいですがムシャムシャ食べています。

生き物に興味津々のコウタロウくんもしっかり撮影。

スジグロカバマダラはおやすみ中なので、そーーーっと観察。

昼間とはまた違う西表。
ヤマネコ以外にもたくさんの生物がいて楽しいですよー。