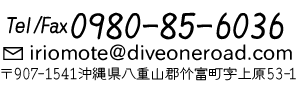西表島野生生物保護センター(環境省)が主催する
「干潟観察会」に子供2人と参加してきました。

テーマは民謡のカニ「やぐじゃーま」に会いに行こうです。
西表島の古見集落に伝わる「やぐじゃーま節」に登場する
クマドリオウギガニ(やぐじゃーま)が本日の主役。
その他かなりの種類の生物が見つかりましたが写真が多くなりすぎるので
また明日アップしますね。
始めの自己紹介はいつもの元気はどこへやら、こんにゃくのように
フニャフニャしながらかろうじて名前だけ言えたウチの兄弟。
しかし、干潟に出てしまえば元気いっぱい(言うこときかずにやっかいです)



コツを掴んだら自分達だけでいろいろ探せるので楽しかったようです。

調子にのって捕まえたカニの名前を聞きに行く長男琉成。

講師の先生達にも臆することなくガンガン入っていく次男穂岳(笑)
一口に干潟と言っても環境は様々。
ミナミコメツキガニがいるような場所

足がズボズボ埋まるような場所

落ち葉がたまるような場所

それぞれにまたちがったカニがいてヤナギも大変勉強になりました。
今回探した場所は200年前には港があった場所らしく(今はなにもありませんが)
注意してみるとパナリ焼きの破片がたくさん落ちています。

講師の先生もパナリ焼きについて説明されていました。

さて、本題のクマドリオウギガ二(やぐじゃーま)ですが無事ご対面。

ハサミと目だけがオレンジ色でおしゃれなカニさんです。

目の下の隈取模様も特徴ですね。
比較的珍しいはずですがここにはたくさん住んでいました。たぶん10匹以上は
見つかったはずです。
クマドリオウギガニの目線で歌われてるちょっと切ないやぐじゃーま節。
あの場所に行って実際にやぐじゃーまに会ってから聞く唄は
昔の人々の生活が思い出されまたちがった唄に聞こえました。